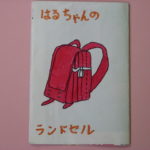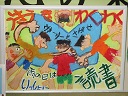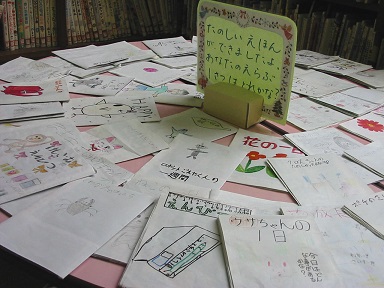環境月間
 ■6月は、環境月間です。新聞の切り抜きやパン
■6月は、環境月間です。新聞の切り抜きやパン
フレット、環境を守るためのグッズなどを展示す
ると、子どもたち自身の日常生活の中に、環境保
護を意識づけることが出来ると思います。また、
公共の機関やボランティア団体などが、環境保護
のための勉強会や体験学習会を実施していますので、その情報を「図書館便り」などで知ら
せることも大切です。子ども達は、興味・関心をもったり、疑問をもったり・・と心が動く
と「調べてみよう」「やってみよう」と本に手を伸ばし意欲的に知るための読書をし、知り
得た情報を素直に自分の生活の中で活かしていこうとします。私たちは、<より便利><よ
り快適>を追い求めています。
信号、みんなで渡れば怖くない」の感覚で、一度手にした便利で快適な生活を手放すことが
できません。本来、大人がまず先に行動し子ども達を導くべきだと思いますが、現実にはむ
ずかしいようです。それなら、子ども達が先に気づいて行動し、大人を変え、社会を変えて
いってもいいのではないでしょうか。
環境にやさしい図書室
■図書室では、普段からつ次のようなことを実践しています。
・ミスプリント用紙の活用
・空き箱、空きビン、ペットボトル、かまぼこ板の再利用
・カレンダーやポスターの裏面を使ったミニ絵本やおはなしの小道具作り
・針なしホチキスの利用
- ダンボールと小枝
- ペットボトル
- ポスター
- ポスター
- ペットボトル
- 空き箱・ポスター
■また、環境にやさしいグッズとして次のものを紹介しました。
セラミックでできていて水の中に入れておくと水が活性化して洗剤が不要になる
アクリル毛糸で編んだもので、台所洗剤やお風呂用洗剤が、不要になる
EMとは、有用な微生物の集合体。土に埋める前に残飯に混ぜておくとより早く土にかえすことができるのがEMぼかし。EMだんごは、川や海などにまいて、生活排水で汚れた水を蘇らせる
純石けん99%で無添加なので安全。排水にふくまれる石けんは微生物のエサとなり全て分解され自然にもどる
茶渋落とし、水垢落とし。酢と混ぜて使うとより効果的
使用済みの食用油に水と苛性ソーダを混ぜて作った手作り石けん
新聞紙、牛乳パック、段ボールなど資源ゴミとして出しても自分の生活にそれを取り入れなくてはリサイクルも不十分。金額的に高くてもあえてリサイクル品を利用することが大切
水道の蛇口に取り付けて出る水の量を制限するもの。水道局や市役所で配布している
■子ども達にも先生方にも珍しいもののようでした。
テーマの本のコーナー「環境を守る」
<”環境を守る”ブックリスト(本校所蔵のみ)>
本と子どもたち
■読書の大切さを否定する人はいないと思いますが、特に心も体も日々成長し続けている子
どもにとって、それぞれの発達段階や興味、関心に応じて、すぐ側に読む本があるという事
はとても大切だと思います。
どきどき、わくわくしながら想像力をふくらませて本の世界を旅すること、読書によって知
らなかった事を知ること、そんな読書体験を積み重ねていくことは、子どもの成長を大きな
力で支えていると思います。
子ども達は、実体験と読書で得た知恵や知識を結びつけて、言葉を獲得したり、自
分自身を知ったり、相手を思いやったりできるようになっていくのではないでしょ
うか。「自分を認める」「相手を認める」「自分の気持ちを伝える」「相手の気持
ちを聴く」・・・生きていくということは、その繰り返しだと思います。その繰り
返しの中で、成長していくのだと思います。
サン・テグジュペリの「星の王子さま」の中にこんな言葉があります。
「こうして目の前に見ているのは、人間の外がわだけだ。
一ばんたいせつなものは、目にはみえない」
この目に見えない大切なものを見る目は、豊かな読書経験と色々な人とのふれあいの中で、
育っていくのではないでしょうか。実体験は難しくても、想像力があれば読書の中で、無限
に体験ができます。
私は「自分を認める」「相手を認める」「自分の気持ちを伝える」「相手の気持ちを聴く」
という人として生きていく時に、なにより大切なそんなことを本を手渡しながら、子ども達
に伝え続けていきたいと思います。
布の絵本
■布の絵本の第一人者渡辺順子先生の講演と実習に参加しました。
”すべての子どもたちに絵本世界を”
と、熱く語られる先生の思いに強く共感しました。
■布の絵本は、遊具と教具の二つの要素をもっていて、作った人の心と使う子どもの心が結
ばれるのだとおっしゃいます。私も一針一針に命の尊さ、平和への願いを込めて刺し続けた
い、布の絵本普及の一粒の種になりたいと思いました。布の絵本について学んだり、絵本を
作品を作り上げるうちに、子ども達にもこの本の素晴らしさを伝えたいと思いました。
■まず、障害をもつ子どものための本づくりに力を入れて活動されている北海道の”ふきの
とう文庫”の製作キットで「いないないばぁ」という布の絵本を作りました。
原作は、松谷みよ子さんの「いないいないばぁ」(福音館書店)です。
- 布の絵本コーナー
- 「いないいないばあ」
■渡辺順子先生の講演会で、布の絵本の素晴らしさを実感した私は、何日もかけて作り上げ
た「いないいないばぁ」の布の絵本を持って、全クラスで子どもたちに読み聞かせをしまし
た。赤ちゃんのための絵本なのに、珍しさもあるとは思いますが、子どもたちには大変好評
でした。反応の良さに気をよくした私は、いろいろな場所で「いないいないばぁ」を読んで
みました。どこで読んでも、誰に読んでも人を引きつけ、場を和ませる布の絵本・・・
私は、その魅力にますます引き込まれました。
■熊本市には、「ひまわり文庫」というボランティアグループがあり、障害をもった子ども
達のために、長年、布の絵本や布のおもちゃを作り、貸し出しをされています。
私は、”秋の読書週間”に「バリアフリー絵本の展示」をしたいと思い、「ひまわり文庫」さ
んを訪ね、たくさんの布の絵本や布のおもちゃを借りてきました。
■私の作った3冊の布の絵本「いないいないばぁ」「いくつ?」「できるかな?」や点字絵
本、布のおもちゃ、手話の本も展示しました。
「さわる布のカレンダー」をみんなで作ろう!
私の頭の中には、子ども達と一緒に「さわる布のカレンダー」を作りたいという気持ちがあ
りました。子ども達に「作ってみない?」と持ちかけてみたところ、大乗り気!・・・
でも、準備はとても大変でした。
針なんて持ったこともない1年生も、わんぱくな男の子達も、やりたい子は誰でも参加でき
ますから・・・。それも、休み時間だけでしあげるのですから・・・。
でも完成したのです!!
- 12月のカレンダー
- 男の子も・・・
- 1年生も・・・
■出来上がった世界にたった一つの「さわる布のカレンダー」は、
6年生のクラスから順番に1週間ずつ各教室に貸し出し、その使い心地を体験してもらいま
した。図書室に帰ってきたカレンダーの日付と曜日と天気は、その日の図書当番が、毎日と
りかえます。日付はボタンで表しますよ。
そして、このみんなの布のカレンダーは、熊本県立図書館で行われた「布の絵本展」にも出
品依頼があり、1カ月間たくさんの方々に見て頂く機会をいただきました。