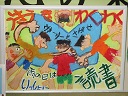子どもと楽しむブックトーク
目次
■「子どもと楽しむブックトーク」の講座に参加しました。
講師は、司書の鹿野恵子先生。
鹿野先生は、全国に先駆け学校図書館に司書が配置された図書館教育の先進県で岡山で長年司書をされています。
特にブックトークには力を入れていらっしゃるそうです。
以下は、講座の記録です。
「はじめの一歩。ブックトークとは?」
■ブックトークとは、あるテーマに関連づけて複数の本を選び、それらの本をつないで紹介することで、聞き手に本の魅力や特徴を伝え、読みたい気持ちを刺激することを目的にしているフロアワークです。
子どもに本を紹介するのとは違い、テーマがあることでの本が響きあい一冊がもつ世界観が広がったり、本と本との絡み合いが生まれたり、聞き手とのやりとりによる集団的効果があります。
ブックトークの実演(中学生のために)四十分間
■テーマ「住むところが・・・・」
(住んでいるところは、どうなっているのか。)
『おばあちゃんは木になった』(大西暢夫)
「先生のふるさとの地名は、もう地図帳には記載されていません」
という導入からブックトークが始まった。
ダムに沈む予定の村に暮らし続けるお年寄りの自然に寄り添った生活を綴った写真絵本の読み聞かせ。
お年寄りの愛する徳山村の位置を地図で確認し
「もう、地図には載っていません。」
と結んで、次の本へ。
『こうすればつかえる、よくわかる地図の読みかた 遊び方事典』(清水靖夫)
日本の地図には見られない外国の地図記号、外国の地図には見られない日本の地図だけに見られる記号の紹介。
地図の折り方には、きまりがあるというトリビアの披露。
「地図ではわからない地球上のことを知るにはね」
と、次の本へ。
『地球がもし100cmの球だったら』(永井智哉)
現在、地球がどんな状態なのか、地球に暮らす人々がどんな生活をしているのかがよくわかる本。
「人間にとって住みにくい地球だけど、その危機的状況は動物にまで及んでいますよ」
と、次の本へ。
『キツネとタヌキの大研究』(小暮正夫)
きつねうどんとたぬきうどんについてトリビアを披露したり、狐と狸の漢字について説明したり・・・
「私達が暮らしている環境はかわってきているんですね。
一本の黄色い花が、すっかり環境をかえてしまったという話があるんですよ。」
と、次の本へ。
『ドーム郡ものがたり』(芝田勝茂)
武器をもたない平和なドーム郡という町が、災いをもたらすといわれる一本の黄色い花によって変わり果てていく・・・鹿野先生一押しのファンタジー。
素晴らしい! 引き込まれました!
手にしてみたくなりました! 読んでみたくなりました!
その他のブックトークのプログラムは以下の通りです。
■テーマ「おおきくても ちいさくても」(対象 小学校中学年)
■テーマ「ともだち そして なかま」(対象 小学校高学年)
■テーマ「時間とわたしたち」(対象 中学生)
■テーマ「夏・ナツ・なつやすみ!!」(対象 小学校中学年)
■テーマ「願い」(対象 小学3年生) 導入・・・パネルシアター「はるのたね」
■実演をされた司書の方から次のようなコメントがありました。
「毎日子どもたちの本の利用を見ていると、装丁や活字などの外観のせいで読まれない本、あるいは逆にカバーの絵で選ばれる本がある。
本を見かけで選びがちな子どもたちに、身近な人が、その人の言葉で本の魅力を語ることで、子どもの”読みたい気持ちを引き出す”のがブックトーク」
①対象の子どもたちにとって興味のあるテーマか?
②選ばれた本は、子どもたちのどこに響くだろうか?
(5感にうったえることが大切)
③読まれたり紹介された部分は、その本の大事なところだろうか?
(つなぎのための糊のような扱いでは、その本に失礼。
その本の主題となるところを紹介したい)
④全体の流れは、違和感なくスムーズか?
⑤本と本のつなぎは自然か?
⑥話し手のひとりよがりでなく、聞き手とのやり取りも行えたか?
(子どもたちが、「参加した」という気持ちになれたか)
⑦最後に、子どもたちがどれか1冊は「読んでみたい」と
思える本に出合えたか?
(子どもたち一人一人の顔を思い浮かべてながら・・)
やってみよう!「ブックトーク」
テーマを決める
■テーマを先に決めてもいいし、紹介したい核になる本を決め、本や構成を考える中でテーマを決定してもよい。
聞き手の構成を考えてバラエティーに富んだ本を選ぶ
■例えば、本の苦手なクラスには、物語より科学の本を多めに。
本に語らせることが大事。
最初に小物や実物資料、クイズ、手品、パネルシアターなど
■聞き手を引きつけるものを効果的に使う。
本の中身が分かりやすくなるし場に彩りが生まれる。
聞き手の反応によって
■短縮したり、ふくらませたりと、台本通りにはいかないものだが、台本をつくってイメージトレーニングをしたり、つなぎの言葉をチェックしたりすることも大切。
その他
■日頃から本の貯金(お気に入りの本、たくさんの本)を心がけておく。
仲間同士の学習会で、本の紹介をし合う、書評の書き方を学ぶ、合評会でシビアに意見交換・・といった努力を惜しまない。
作家やジャンルは、テーマにはならない。
作家やジャンルは、バラエティとんでいた方が、いろいろな好みをもった子ども達に受け入れられる。
小学校低学年へのブックトークは、本の冊数を増やしたり、時間を短くしたりすると可能。(例えば「雨ふり楽しいなあ」というテーマで・・・)
■ブックトークのタイトルやテーマは、聞き手に伝えなくてもよい。
子ども達の読書体験を広げるために、教師や司書のブックトークの重要性が、光村図書の小学校国語教科書の指導書に書かれている。
■テーマもつなぎもないのは、本の紹介。
高齢者へのブックトークは、事前にチラシやプログラムなどを準備しておくとよい。
数冊の絵本だけのブックトークもあり得る。
最後まで自分の手にとって読んでみたいと思う。
聞き手の年齢幅が広い時にもブックトークは、可能。
幅広い年齢に使える本もあるし、難しい本でも説明する言葉に気をつければ、低学年にもわかるし、自分で読むには難しくても読んであげれば理解できる本もある。
■中学生が喜ぶテーマは、動物、異性関係、人気のテレビ番組、人気の漫画、記憶力など。
ブックトークって面白いなぁ。
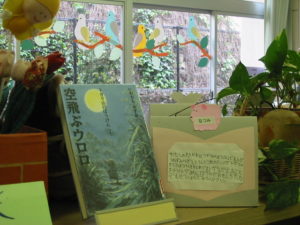 ■本同士の響きあいから、浮かび上がってくる一冊の本の魅力に思わず「読んでみたい」と思わせてくれます。
■本同士の響きあいから、浮かび上がってくる一冊の本の魅力に思わず「読んでみたい」と思わせてくれます。
今回、講座に参加して、これまで、ブックトークのつもりで私がやったのは、本の紹介だったということがわかりました。
テーマはあったのですが、本と本のつなぎがありませんでした。
「いのち」というテーマでブックトークをする時に命をテーマにした本を数冊紹介しました。
ブックトークのテーマと、紹介する本のテーマが同じになる必要はないのです。
本と本をつなぐためには、つなぎの言葉が必要です。
1冊の本の中には、いくつもキーワードがありますが、それはつなぎの言葉になり得ますから、1冊の本が色々なテーマのブックトークに使える訳です。
鹿野先生は、
「台本は必要ないけれど、つなぎの言葉のチェックは必要」
とおっしゃっていました。